記事公開日:2025年10月10日
トリオシステムプランズ株式会社 様
「多拠点企業の成長を支えるLMSとeラーニングの活用術~人材育成と社内コミュニケーションを進化させる独自の取り組みとは~ 」

トリオシステムプランズ株式会社は、「人に優しいシステムをつくる」という理念のもと、医療・金融・流通・製造など幅広い分野でシステム開発を行っている総合システム開発企業です。全国に6つの事業所を持ち、各地域の産業特性に応じたソリューションを提供しています。
同社は2020年度より、富士通ラーニングメディア(以下、FLM)の学習管理システム ”KnowledgeC@fe”を導入。eラーニングコンテンツの制作・配信に利用するとともに、FLMの講義動画コンテンツ「e講義動画ライブラリ(注)」も活用しながら、多拠点体制ならではの人材育成課題の解決に役立てています。
今回は、同社がKnowledgeC@feとe講義動画ライブラリをどのように活用し、どのような成果を上げたのかについて、経営管理室の宮﨑様にお話を伺いました。
(注)e講義動画ライブラリ:講習会の講義を動画化したeラーニング(e講義動画)のコースを受け放題で利用できるサービス。ICTを中心に、ビジネス、ヒューマンやAI、ビッグデータなどの最新トレンドまで、幅広い全135コース(2025年6月現在)が受講できる。
全国の社員をどう育てる?集合研修の壁と最新技術の習得への対応
──2020年にKnowledgeC@feおよびe講義動画ライブラリを導入する以前、社員教育にはどのような課題がありましたか?
宮﨑様:当社は全国6ヵ所の事業所でソリューションビジネスを展開しており、お客様先に常駐しながら、業務を行っている社員も多くいます。それぞれ勤務地もスケジュールも異なるため、一堂に会して集合研修を実施するのは非常に困難でした。

現在、経営管理室の課長としてマネジメント業務を行うと同時に、
新卒入社時から一貫して情報セキュリティ担当のシステムエンジニアとしても活躍中。
宮﨑様:そのためKnowledgeC@fe導入以前は、全国の拠点をテレビ会議でつないで研修を行っていました。お客様先に常駐している社員は拠点へ戻り、テレビ会議システムを通じて研修を受講するという体制だったのです。しかし、拠点の近くにいる社員は対応できても、遠方のお客様先に常駐している場合は移動が難しく、限界がありました。
また、業務で使用するプログラミング言語のトレンドは移り変わりが激しく、常にスキルアップのために学んでいないと、仕事を継続的に受注していくのが難しいという状況もありました。そのため、全国各地のお客様先に常駐する社員にも確実な効果が期待できる学習管理システム(以下、LMS)とeラーニングの導入は、当社にとって喫緊の課題でした。
ピンポイント学習を実現する「e講義動画ライブラリ」の導入
──数あるLMSの中から、FLMのKnowledgeC@feを選ばれた理由は何だったのでしょうか?
宮﨑様:KnowledgeC@fe導入以前から、FLMさんとは新入社員研修でお取引がありました。その際のやりとりや研修のクオリティ、営業担当の方の提案内容から、当社の人材育成における課題解決に繋がると感じました。また、同時にご提案いただいたe講義動画ライブラリと組み合わせて活用すれば、より効果的な人材育成が可能になると考えました。

──併せて導入したe講義動画ライブラリは、どのように活用されていますか?
宮﨑様:経験豊富な講師による講義動画が無制限で視聴可能な為、全国各地で働く社員が、場所や状況に関係なく、さまざまなスキルや最新技術を学べるようになりました。もちろん1つの動画を最初から最後まで通して視聴する場合もありますが、例えば「Javaの新機能だけを知りたい」といった場合に、必要な部分だけをピンポイントで視聴できる点も、e講義動画ライブラリの大きな利点であると感じています。
開発言語などのICT関連コース以外にも、AIやビッグデータといった最新トレンドやビジネススキル関連など、コースの幅広さも魅力の一つです。ちなみに私自身もSEであると同時にマネージャーの立場にあるため、アサーティブ・コミュニケーション(お互いを尊重しながら意見を交わす方法)など、e講義動画ライブラリ内にあるヒューマンスキル系のコースをよく参照しています。
KnowledgeC@feの新たな活用法で実現した、社内コミュニケーションの活性化
──FLMが提供するコンテンツのほかに、自社オリジナルのコンテンツもKnowledgeC@fe上で活用されていると伺っています。どのようなものを作成されていますか?
宮﨑様:セキュリティやコンプライアンスに関する情報、あるいは勤怠システムの操作方法などを通知する教育コンテンツも作成していますが、大きな取り組みとして「新入社員の成果発表会」があります。
これは、新入社員一人ひとりが入社後1年間で得た自身の経験と成果をプレゼンテーションし、その内容に対して社員全員がKnowledgeC@feを通してコメントを寄せる取り組みです。新入社員は発表資料を作成し、10分程度プレゼンテーションしてもらいます。それを動画に撮り、KnowledgeC@feにアップして、社内に公開するというやり方を採用しました。
以前対面で成果発表会を実施していた頃は、発表した新入社員は、先輩社員からのコメントを貰うのに、対面で会話をする必要があった為、貰えるコメントも限られてしまうという課題がありましたが、KnowledgeC@fe上で行うようになったことで率直なコメントが多数寄せられるようになり、コメントのリスト化も可能になりました。

宮﨑様:このやり方に変更して以来、新入社員が発表資料を作成する際に、前年の先輩にコツを尋ねたり資料を見せてもらうなど、拠点や世代を越えたコミュニケーションも活発化しています。このような交流は、勤務地や世代がバラバラゆえに、お互いの人となりを知る機会が少ない当社社員にとって、非常に良い影響を与えていると感じています。
ちなみに、導入から5年が経ち、「新入社員が1年上の先輩に発表資料作成のコツを尋ねる」という伝統が繰り返された結果、最新の成果発表会で公開された資料は、5年前と比べて格段にクオリティが向上していました(笑)。
こうした活用や交流は、「様々な形式の自社オリジナルのコンテンツをアップロードできる」だけでなく、「気づきやコメントの共有機能などで、利用者同士の学び合いをサポートできる」といったKnowledgeC@feの特徴が活きた良い例かと思います。
社員のスキルの見える化・共有で、社内に学びの文化を根付かせたい
──導入から5年が経ちますが、社員の学習意欲や知識の定着度に変化はありましたか?
宮﨑様:間違いなく向上しています。しかし、e講義動画ライブラリが利用できることを社員に案内するだけでは、思ったほど受講率は伸びないとも感じました。
当社の場合は、e講義動画ライブラリの受講を社員に委ねるだけでなく、対面での集合研修と組み合わせた形でも利用しています。新入社員研修ではヒューマンスキル系・ビジネススキル系のe講義動画を会社側が指定し、視聴後にレポートを提出してもらっています。また、役員向けを含む階層別研修では、対面での研修の後、より深く学んでもらいたい内容のe講義動画を事後課題とするなど、社員や研修の特性に応じた工夫を重ねています。
――学びの促進に向けて、今後KnowledgeC@feを使って取り組んでいきたいことはありますか?
宮﨑様:KnowledgeC@feには、社員一人ひとりの知識やスキル、経験を登録し、互いに参照し合うことができる「組織・ひと 名鑑」という機能がありますが、今後はこれももっと活用していきたいです。それぞれの社員が持っている資格情報を登録してもらうことで、案件に対して必要なスキルを保持している人へアサインすることにも役立つだろうと感じています。
また、「組織・ひと 名鑑」とKnowledgeC@feの研修受講履歴の連携にも期待したいです。「組織・ひと 名鑑」を通して、誰がどんな研修を受けているか社員同士が分かるようになれば、互いに学習のモチベーションを高め合ったり、ロールモデルを見つけたりすることにつながるのではないかと思います。
「組織・ひと 名鑑」とは:
KnowledgeC@feに搭載されている、個人や組織の情報を登録・共有できる機能。個人の知識・スキル・経験や組織(部署/チーム/プロジェクト)のパーパス・ビジョン・ミッション・アピールポイントなど、多様な情報を社員自身が登録可能。人事情報だけでは見えづらいチーム/プロジェクト単位の動きや、個人の人柄・スキルなどを可視化し、組織全体の連携強化や柔軟なチーム編成に役立てることができる。
トリオシステムプランズを含むトリオグループでは、「組織・ひと 名鑑」を社内コミュニケーションの活性化に役立てている。社員同士が初対面の場でも、「組織・ひと 名鑑」に登録されたプロフィール情報をきっかけに会話が広がるケースがあるという。

同社では「組織・ひと 名鑑」のプロフィール画像として、プロのイラストレーターによる親しみやすい似顔絵を使用している。拡大した似顔絵は宮﨑様。(組織図はイメージで、実際のものとは異なります)
――最後に、今後の展望やFLMへの期待があればお聞かせください。
宮﨑様:当社はシステム開発や、Salesforceビジネス、医療ソリューションビジネス等の事業を展開していますが、おかげさまで業績は順調に推移しています。一方で、お客様のニーズは時代と共に移り変わっていくものですし、生成AIの進展等、テクノロジーの潮流も今後、大きく変化していきます。
だからこそ、特定の製品に関する「今必要な知識やスキル」だけでなく、「より幅広い知識とスキル」を日頃から追っていき、新しいビジネスにも対応できる人材を育てていく必要があると考えています。その意味でも、KnowledgeC@feとe講義動画ライブラリをひとつのきっかけとしながら、会社全体で学びの幅を広げていきたいと思います。
関連情報
富士通ラーニングメディア担当者からのメッセージ
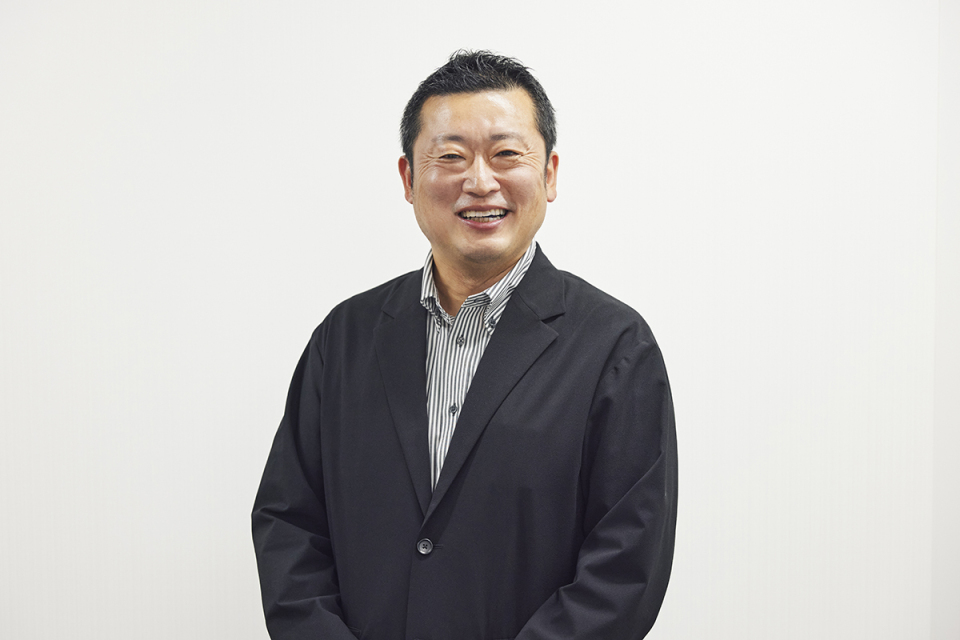
カスタマーサクセス本部
関西・中部エリアビジネス統括部
荒木 健一
2020年にKnowledgeC@feとe講義動画ライブラリをご導入いただいて以来、トリオシステムプランズ様は既成のコンテンツだけでなく自社で制作したコンテンツもしっかり運用し、KnowledgeC@feが持っている特徴を本当に上手く活用されていると思っています。
新入社員の成果発表会でKnowledgeC@feのコミュニケーション機能を駆使したり、e講義動画ライブラリと自社の集合研修を組み合わせたりすることで学びを深化させ、人材育成の「自走」に成功されているのです。
今後も、トリオシステムプランズ様がKnowledgeC@feとe講義動画ライブラリをより効果的にご活用いただけるよう、ご支援させていただく所存です。
(注)本記事の登場人物の所属、役職は記事公開時のものです。
他の記事を読む
株式会社ジーシー 様「『専門領域での活躍』を目指し、未経験から即戦力へ~学習管理システムで歯科医療の知識習得を加速させる~ 」

株式会社 中島董商店 様「実践型DX研修で新規事業の創出に挑む~『真面目な会社』を超えて中島董商店が目指す姿とは~」

【開催レポート】Fujitsu 人材育成セミナー 2024 基調講演 AIエンジニア 安野貴博氏「未来を創るためのテクノロジーとは ~人と社会のアップデートを目指して~」

本ページに関するお問い合わせ
当社はセキュリティ保護の観点からSSL技術を使用しております。
受付時間 : 9:00~17:30(土・日・祝日・当社指定の休業日を除く)
