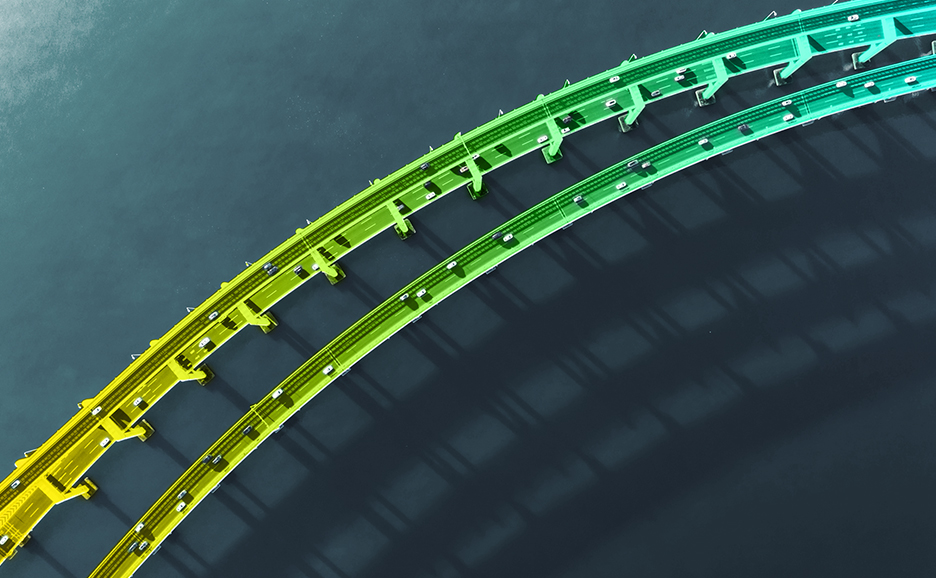ヤマトグループのSST社と富士通が挑む、持続可能な共同輸配送とは

Article | 2025年11月10日
この記事は約10分で読めます
国内の物流事業者が直面する2大課題――ドライバーの長時間労働規制やなり手不足への対応と気候変動対策――に果敢に挑戦する企業があります。国内物流大手のヤマトグループ傘下のSustainable Shared Transport(サステナブル・シェアード・トランスポート)株式会社(以下、SST)は、複数の荷主の貨物を1台のトラックで運ぶ共同輸配送の仕組みをつくり、持続可能な物流を実現しようとしています。
SST経営企画部長の長瀬晴信氏と富士通AGM(Account General Manager)西村剛が対談し、事業成長と社会課題解決を両立させるネットポジティブ(*1)な物流を実現する勘所について意見を交わしました。
SSTが目指すネットポジティブな物流変革とは?
富士通・西村:
いま、単に環境負荷を低減するだけではなく、社会や環境に対して、積極的に良い影響を与えていくネットポジティブな考え方が、ビジネスのカギを握るようになっています。
複数社の貨物を1台のトラックで共同輸送するオープンプラットフォームサービスを提供するSST社において、長瀬晴信さんは、ネットポジティブな物流変革を推進されています。長瀬さん、SSTの取り組みで革新的な 点を教えていただけますか?
SST・長瀬:
特徴的な点は、物流事業者が荷主企業と一緒になって課題解決に取り組んでいることですね。
SSTは、ヤマトホールディングスの子会社として2024年に設立され、共同輸配送の仕組みを提供しています。いわゆる「物流2024年問題」と呼ばれる“物流の需給ひっ迫”問題、そして“気候変動”――この2つの社会課題の解決を目指しています。
企業と企業の間でやり取りする貨物は、各社が1台のトラックを貸し切りにして運ぶことがほとんどです。これはそれぞれがプライベートジェットを借りるようなもので、外部環境が変化する中で、いつまでも機体が確保できるとは限りません。
SSTは、事前に定めた運行ダイヤで、必要なスペースを予約いただき貨物を運びます。航空機の座席を予約して利用するような形ですね。事前予約という形をとることで荷主と物流の双方にとって安定した運用につながると考えています。
西村:
課題と感じた点はありましたか。
長瀬:
荷主企業は予約・計画型の物流へと商慣行を一部、変えることになりますので、理解と意識変革が必要です。こちらについては道半ばだと思っています。他にも効率よく荷積み・荷卸しを行うためのパレット(*2)の標準化といった課題もあります。ひとつひとつ解決していきたいと考えています。
富士通がSSTに参画したきっかけは、2018年に開始した内閣府の産学官連携プロジェクト「戦略的イノベーション創造プログラム(Cross-ministerial Strategic Innovation Promotion Program: SIP)」です。同プロジェクトにおいて、富士通はヤマトグループなどと物流業界の課題を議論し、サプライチェーンの全体最適のあり方を検討しました。得た知見を実業にいかそうと、2025年、富士通はSSTに出資し、持続可能な物流の実現をともに目指しています。

SSTのプラットフォームを支える富士通のテクノロジーとは
西村:
SSTのオープンプラットフォームに搭載した技術としては、まずアクセス権限コントロールです。これは信用の土台となる、他社に「見せるべきもの」「見せてはいけないもの」をしっかりコントロールするものです。
また、万が一、データが改ざんされた際に追跡や復旧を容易にするブロックチェーン技術があります。受注から計画、予約、マッチング、追跡という一連の動きを支えるのは、富士通のUvance(*3)のオファリングです。
成果としては、業務効率化はもちろん、約10トンのCO2排出削減を実現しました。今後さらに、需給調整にかかるリードタイムの調整や可視化などで連携を進めたいと考えています。
長瀬さん、多くのステークホルダーが参画すると総論で賛成、各論反対となりがちですが、連携する難しさはなかったのでしょうか?
長瀬:
そうですね。我々のビジョンについては多くの方に賛同していただいていますが、コスト増やオペレーション変更に関しては、ハードルが高いと感じる方もいらっしゃいます。
例えば、あるメーカーさまの案件では、大阪から仙台の区間を我々が担当させていただくにあたり、浜松、厚木、福島と3回貨物を積み替えながら中継輸送をします。このため、お客さまはこの貨物の積み替えを問題なく対応できるのか心配されていました。お客さまとはオペレーションについてきちんとお話しし、ご理解いただくことができ、順調に運行ができています。荷主の方にはこれまでのオペレーションを変更いただくことになるため、丁寧にコミュニケーションをとりながら説明することが重要と感じています。
ほかにも、富士通さんと開発した温室効果ガスの排出量可視化ツールを用いて削減量を見える化したり、積載率向上や荷持ち時間の短縮といった荷主の努力義務に関して情報提供したりするなど、荷主の方々の物流効率化支援を通じて、SSTを輸送選択肢の一つとしてご利用いただけるように取り組んでいます。

西村:
富士通のテクノロジーの価値としては2つあって、ひとつは、データやセキュリティが信頼を担保して、お客様とコミュニケーションをとる土台を作れるということ。もうひとつは、個社では難しいビジネス拡大や効率化を支援して企業が参加しやすい環境を作ることです。
長瀬さんが仲間づくりにおいて、囲い込むのではなく、お客様に選択肢を提供する姿勢に非常に共感しました。
共創がネットポジティブを実現するカギになる
長瀬:
私は前提として、ネットポジティブという考え方は、よりよい社会を実現するために必要と考えています。弊社が取り組んでいる物流の効率化は、温室効果ガスの削減だけではなく、サプライチェーン全体の強靭化、日本経済の活性化につながると捉えています。
キーワードのひとつは、「共創=Co-creation(コ・クリエーション)」です。我々利用運送事業者には、荷主だけでなく運送パートナーが必須です。自社の強み、特徴、足りない機能を正確に理解して、最適なパートナーを求めていかねばなりません。時代の変化は非常に早いですが、失敗を恐れないチャレンジがますます重要になると思います。
西村:
おっしゃる通りですね。企業がネットポジティブを実現する上で重要なマインドセットは、変化を恐れず、積極的に関わり、共創することだと、改めて感じました。
ネットポジティブはパートナーシップなしでは達成できません。共に考えて課題に向き合い、最終的には共に稼ぐこと、パートナーと本来の関係性をつくるということが大切だと思いますし、そうありたいですね。長瀬さん、ありがとうございました。

富士通は、ネットポジティブ推進プログラムを通じて、企業のサステナビリティ経営の実現を支援しています。自社のネットポジティブへの成熟度や立ち位置を客観的に把握できるネットポジティブ評価ツールは、17の質問に答えることで、企業の現在の取り組みフェーズと点数が表示されるツールです。ぜひお試しください。
(*1)ネットポジティブ:企業活動による「マイナスの影響」を最小限に抑えるだけでなく、社会や環境に対して積極的に「プラスの影響」を与えることを目指した考え方
(*2)パレット:輸送・保管の際に貨物を載せる荷役台のこと
(*3)Uvance:社会課題を起点とした富士通の事業モデル

関連コンテンツ
Net Positive
~ネットポジティブで社会とビジネスの未来を創る~