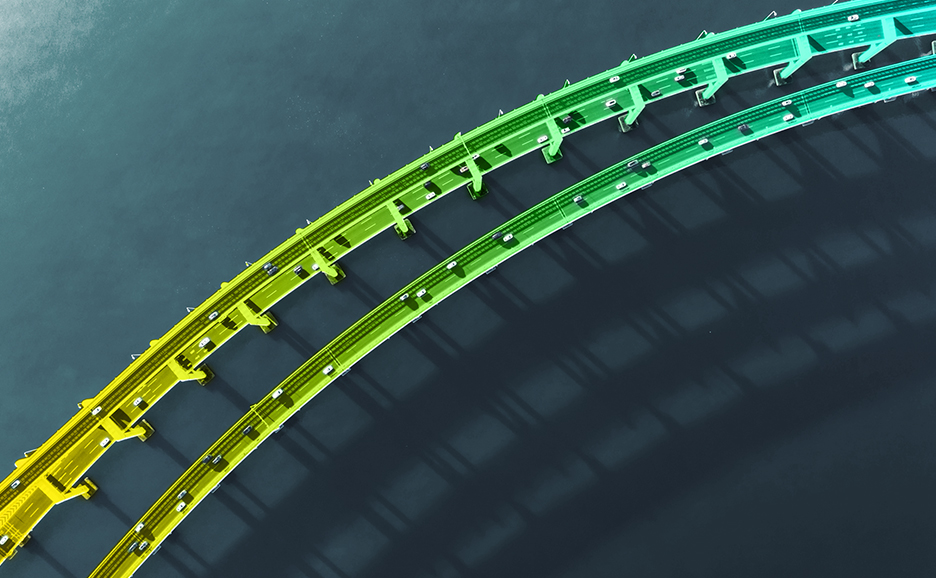Scope 3排出量ネットゼロとレジリエンス構築で実現する サプライチェーンのサステナビリティへの取り組み

Article | 2025年11月12日
この記事は約10分で読めます
ネットポジティブとは、企業活動による「ネガティブなインパクト」を減らすだけでなく、社会や環境に対して積極的に「ポジティブなインパクト」を創出することを目指す考え方です。調査によると、この考え方を持つ企業は収益が高く、投資家の信頼も得やすいことが分かっています。富士通は取り組みの一つとして、GHG排出量に関してバリューチェーン全体でのネットゼロ実現を目指し、GHG排出量の可視化などデータとテクノロジーを活用した取り組みを進めています。
富士通がEconomist Impactと共同で実施した調査によると、ネットポジティブへの取り組みが十分に成熟している企業は、業界を問わず収益と市場シェアの目標達成見込みが高く、投資家の信頼を得ている傾向がありました。企業にとって、ネットポジティブの追求はビジネス成長と社会・環境の両面にメリットがあるのです。しかしながら、同調査では、多くの企業役員・意思決定者がこの両面へのメリットを理解しているにも関わらず、ネットポジティブを推進することの難しさに直面していることがわかりました。
特に、サプライヤーやパートナーなど様々なステークホルダーが存在するビジネスにおいては、自社内の変革だけでなくサプライチェーン全体で企業同士が価値観を共有して連携し、ネットゼロを推進する必要があります。
富士通は、バリューチェーン全体でGHG排出量のネットゼロを進めていくために、社内だけでなく社外のステークホルダーと多くの議論を重ねながら、データとテクノロジーを活用して取り組みを推進している企業の1つです。
具体的には、持続可能な開発のための世界経済人会議(WBCSD)が主催する炭素の透明性のためのパートナーシップ(PACT)の社会実装プログラムを通して、当社は、2023年にバリューチェーン全体のGHG(温室効果ガス)排出量の可視化に向けて、サプライヤーの一次データを活用した製品カーボンフットプリントの企業間データ連携の社会実装を世界で初めて成功しました。現在は19社のサプライヤーとGHG排出量のデータ連携をしており、さらにその取り組みを拡大していき、SBTi で認定いただいた通り、2040年にバリューチェーン全体でネットゼロの実現を目指しています。PACTのルールメイキングと社会実装プログラム参画の機会を通じて、社内外の協働で変革を推進し、業界全体の脱炭素化を加速させることで社会全体にインパクトを創出します。また、環境だけでなく、自然災害、情報セキュリティ、財務、コンプライアンスなどサプライチェーンを取り巻く多角的なリスクに対応するために、パートナーリスクマネジメントを推進しています。社内実践として、富士通のサプライチェーンに関係する外部のリスク情報と当社の販売・生産・調達データを統合し、リスクを一括検知し、分析、早期アクションへとつなげる統合的なリスクマネジメント基盤Third Party Risk Management(TPRM)プラットフォームの構築を進めています。
本稿では、富士通がサプライチェーンのサステナビリティに取り組む背景とその成果について、当社執行役員常務CSSOの山西 高志から紹介します。
企業間のESGデータ共有が課題
―― 富士通は、いつからサプライチェーンのサステナビリティに取り組んでいますか?
富士通グループでは、従来からSDGsやパリ協定などの国際的な動向を踏まえ、CSR基本方針のもとで目標を設定し、グローバルに活動を推進してきました。
2023年度に発表した中期経営計画では、「お客様・社会への価値提供」の視点をより強く反映した「経営におけるマテリアリティ」を新たに定めました。このマテリアリティを基盤として、サプライチェーンのサステナビリティ推進に本格的に着手し、2024年4月には取り組みのさらなる加速を目的として、CSSO(最高サステナビリティ&サプライチェーン責任者)を新設しました。
現在は、人権リスクの予防・軽減、GHG排出量の削減といった環境面への対応、多様性の確保を柱に、社内体制の整備と取引先との連携強化を進めています。
――サプライチェーン全体のGHG排出量に関するデータ連携と可視化に成功しました。この取り組みを推進するにあたって、どのような課題・困難がありましたか?また、それをどう解決しましたか?
当社は、昨年度サプライヤーとのデータ連携に関するプレスリリースを公開しましたが、さらに約20社との連携を掲げ、現在(2025年10月末時点)19社のサプライヤーとのデータ連携に成功しています。この取り組みにより、サプライヤーのGHG排出量削減施策の効果が可視化され、Scope3排出量(サプライチェーン全体のGHG排出量)の算定精度が向上し、調達品単位での排出量の把握が可能となります。
加えて、ESGデータの収集・更新にかかる業務負荷の軽減や一元管理による効率化も実現しています。
取り組みの過程では、サプライヤーからの賛同、データ共有に伴う競合他社への情報漏洩への懸念の払しょくなどに対応してきました。具体的には、Uvanceのオファリング「Sustainability Value Accelerator」を活用し、秘匿性を確保するシステム開発を推進し、安心してデータを共有できる環境を整備しました。また、国内サプライヤーのニーズに対応し、グローバル方法論(WBCSD PACT)と国内ルール(Green×Digitalコンソーシアム)の方法論も活用できるようにしました。
サプライヤーからの賛同については、各社と個別に対話を重ね、排出量の把握状況や上流取引先からの情報取得可能性を確認しながら、取り組みの重要性を共有していきました。
そして、国際・国内両規格への対応については、両方に沿う形での連携方式の整備や相互運用性を確保しました。
具体的には、脱炭素化の加速に注力する日本企業の連合体であるGreen×Digitalコンソーシアムのデータ可視化プロジェクトのリーダーとして、国内規格であるGreen×Digitalコンソーシアムと国際規格であるPACTの異なるメソッドや仕様に対し、日本国内の状況に合わせた規格の採用に成功しました。
この結果、データ連携がしやすい環境を構築し、130以上の企業がPCFを重点テーマとして意識していくようになりました。
これらの成果は、富士通自身のカーボンニュートラル実現とサステナブルなオファリングの提供に向けた重要な一歩となっています。
当社は2040年のネットゼロ達成に向けて、今後もより多くの国内外のパートナーとの連携を図り、削減シミュレーションや削減事例を創出していきながら、本取り組みを加速させていきます。

――TPRMを活用したサプライチェーンのパートナーリスクマネジメントの社内実践について伺います。この取り組みを推進するにあたって、どのような課題・困難がありましたか?
サイバーセキュリティ、ESG、コンプライアンス、自然災害など、サプライチェーンに関わる多様なリスクを一元的に可視化するソリューションは既に市場に存在していますが、富士通はその先を見据えています。単なる可視化にとどまらず、売上などの社内情報と連携させることで、リスクの優先順位を分析し、デジタルリハーサルやAIを活用した最適なアクションへとつなげていく構想を描き、その実現に向けて取り組んでいます。
TPRMの社内実践で当初課題になったのは、社内システムにおける表記やデータ形式・項目の不統一でしたが、現在は、当社がデータドリブン経営の一環として推進しているグローバルでのデータ統一によって解決されています。
TPRMは現在開発中ではありますが、サプライチェーンリスクに対するレジリエンスの強化および持続可能性の実現に貢献するものと確信しています。

サプライチェーンのサステナビリティは事業成長の前提
――サプライチェーンのサステナビリティへの取り組みは、ビジネス成長にどのように寄与するのでしょうか。
当社にとって、サステナブルなサプライチェーンの実現は、多様なパートナーやサプライヤーと一体となって推進する事業そのものの持続可能性を支える根幹であり、事業成長の前提となるものです。
現在、当社ではUvanceを自社のサプライチェーンで活用する社内実践に注力しており、CO2排出量の可視化やTPRMを通じて、サプライヤーやパートナーを巻き込みながらUvanceの活用を進めています。こうした取り組みの中で得られた成功体験のみならず失敗を含む実践知をUvanceの商品開発へとフィードバックすることで、富士通の製品・サービスの品質向上、さらにはより高付加価値なオファリングの創出につなげています。
これらの活動は、Uvanceのビジネス部門とサプライチェーン部門が一体となって推進しており、ユーザー視点での課題やビジネス上の課題について協議を重ね、テクノロジーを駆使しながら改善策の検討を進めています。富士通におけるサプライチェーンサステナビリティの取り組みが、お客様および社会全体のサステナビリティ実現に貢献するよう、ネットポジティブのループを回し、インパクトの最大化を図っています。
――サプライチェーンのサステナビリティについて、今後富士通が目指す方向を教えてください。
当社は、2040年までにバリューチェーン全体におけるネットゼロの達成を目指しています。この目標の実現に向けては、サプライチェーンのサステナビリティにおいて「データドリブン」「グローバル連携」「ガバナンス強化」の三要素が不可欠です。
サプライチェーンにおけるGHG排出量、いわゆるScope 3への対応においては、サプライヤーやパートナーとのエンゲージメントを一層強化し、共にGHG削減に取り組むことが重要です。また、テクノロジーの活用を通じて、実排出量の可視化および削減効果の正確な反映を可能とする、実効性のある取り組みを今後も推進していきます。
GHG排出量削減にとどまらず、情報セキュリティ、自然災害、制裁リスクなど、サプライチェーンを取り巻くリスクや規制はますます複雑化しています。こうした状況に対応するため、現行の手法にとらわれることなく、新たなリスクや規制にも柔軟に対応し続けられる仕組みへと進化させ、サプライチェーン・レジリエンスの構築を目指します。

── 最後に、ネットポジティブに取り組む企業に向けたメッセージをお願いします。
サプライチェーンのサステナビリティは、多くの企業が直面する共通の課題であると同時に、ビジネス成長の大きな機会です。富士通も、GHG排出量の可視化やリスク管理において、サプライヤーやパートナーとの緊密な連携が不可欠であることを実感してきました。
ネットゼロへの道は、富士通のみで築き上げるものではなく、サプライヤーとの協働が不可欠です。
実践で得た知見とUvanceの価値を、お客様そしてパートナーの皆様へと繋ぎ、「ネットポジティブのループ」を共に回すことで、社会全体のポジティブな変革を加速させます。
この大きな挑戦を、ぜひ共に進めていきましょう。

関連コンテンツ
Net Positive
~ネットポジティブで社会とビジネスの未来を創る~