サプライチェーン全体の脱炭素化は持続可能な未来を残すための共通課題
―古河電工×富士通の取り組み―
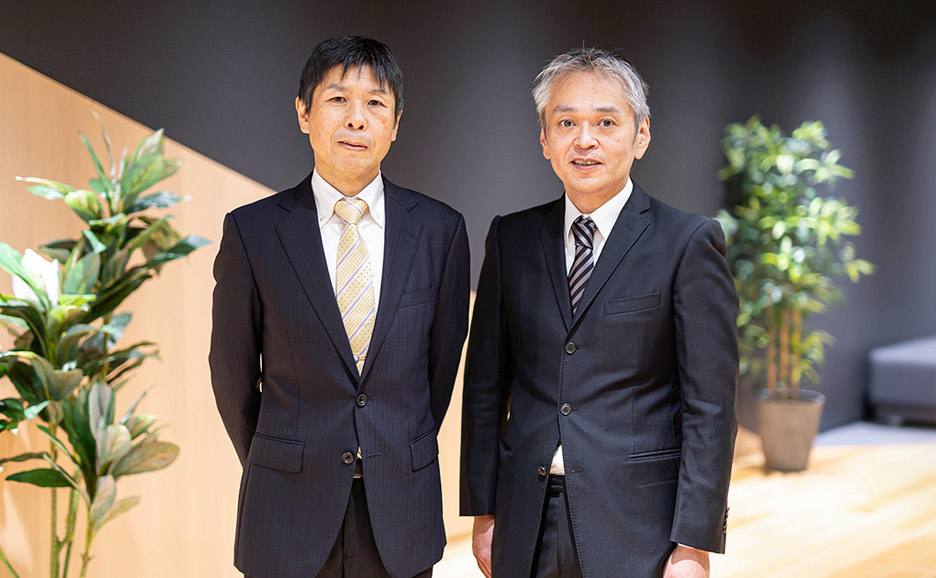
2025年3月13日
日本を含む120以上の国と地域が、2050年までのカーボンニュートラル実現を目標として掲げています。こうした状況の中、富士通はESG Management Platformを活用し、製品単位のCO2排出量(PCF)の実データを連携させ、サプライチェーン全体のCO2排出量の可視化と削減に向けた取り組みを開始しました。この取り組みにサプライヤーとして参加したのが古河電気工業株式会社(以下、古河電工)です。今回、参加を決断した経緯や、参加に当たっての懸念点、効果や成果について、古河電工の情報通信ソリューション統括部門 ファイテル製品事業部門 ものづくり・STC推進部課長の鈴木 幹哉氏、主査の寺田 幸平氏にお話を伺いました。
(注)所属およびインタビュー内容は、取材当時のものです。
サプライチェーン全体の脱炭素化の取り組みが、持続可能な未来を支える
――2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、サプライチェーン全体での脱炭素化の取り組みが進められています。その重要性について、どのように認識していらっしゃいますか。
鈴木氏:古河電工は、サプライチェーン全体での脱炭素化が企業の持続的な成長に不可欠であると認識しています。特に2050年までのカーボンニュートラル実現は、各企業が連携し、長期的な視野で協力することが重要です。我々は環境負荷の低減が企業の社会的責任であり、後世に持続可能な未来を残すための共通の課題であると考えています。
その取り組みの一つとして、2020年には気候変動がもたらすリスクと機会を可視化し、財務に与える影響を開示する国際的なフレームワークである気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)に賛同し、TCFD提言に沿った情報開示を進め、ステークホルダーとの信頼関係を強化しています。

情報通信ソリューション統括部門
ファイテル製品事業部門 ものづくり・STC推進部課長
鈴木 幹哉氏(取材当時)
あわせて、2050年のカーボンニュートラル実現に向けた「環境ビジョン2050」と、そこからのバックキャスティングによる「環境目標2030」を策定し、CO2排出量削減に向けた取り組みを推進しています。工場の省エネや燃料転換、再生可能エネルギーの利用比率向上にも取り組み、2023年度には三重事業所で2万トン以上のCO2削減を達成しました。ファイテル部門としては、顧客使用時の省エネ製品の開発にも取り組んでいます。
寺田氏:他にもわかりやすい取り組みとしては、以前から日光事業所では自前の水力発電所を保有して、使用する電力を100%賄っています。再生可能エネルギーとしては、他にも各事業所で太陽光パネルを活用した発電などにも取り組んでいます。
――脱炭素化の取り組みの重要性は認識しつつも、利益に結びつきにくいなどの理由から、二の足を踏んでしまう企業も多いと思います。サプライチェーン全体での脱炭素化を考えたときには、そうした企業にも賛同してもらう必要があります。
鈴木氏:やはり、「先を見越す」という視点が何よりも大切です。当社にとっても利益はもちろん重要ですが、その一方で「今、この取り組みをやめてしまうと、これから先に繋げることができなくなるのでは」という危機感が強くあります。当社には、企業として何らかの資産を未来に残す、次の世代に繋いでいくという強い使命があります。環境も大切な資産の一つです。その想いで取り組んでいます。
寺田氏:企業は常に社会への貢献を考えなくてはなりません。古河電工には通信ケーブルや海底ケーブル、自動車部品、銅製品など多岐にわたる製品群がありますが、それらの製造工程でのCO2排出量を削減し、温暖化防止や環境保全で社会貢献できれば、大きな意義があります。そんなモチベーションで取り組んでいます。
未知の取り組みに不安もあったが、「踏み出さなくては次に繋がらない」と参加
――そうした取り組みを展開してきた中で感じていた課題はどのようなものでしたか。
寺田氏:まずは、製品群が多岐にわたるために、さまざまな基準でCO2排出量を算定しなくてはなりませんでした。また、当社に素材や部品、材料などを納品しているサプライヤーやパートナーは大企業から小規模事業者まであり、一定の基準を一律に当てはめてCO2排出量を算出することが難しい状況でした。サプライヤーやパートナーごとに環境意識の温度差もあります。
このような課題解消のために、まずは自社のCO2排出量をきちんと算出して顧客に提供しようと考え、透明性と客観性、正確性を備えたデータを計測・算出できるように準備を進めてきました。
こうした中、デバイス製品のPCF算定や、サプライチェーンの温室効果ガス排出量算定では、排出原単位を取りまとめたデータベース(二次データ)を使用して計算していました。これを実際にサプライチェーンの情報をもとにした一次データに移行しなくてはならないと課題を感じていたころに、富士通が同様の課題観をお持ちであることと、サプライチェーン全体でのCO2排出量削減に向けたデータ連携の取り組みについてお話しがあり、当社の課題解決に役立つと感じました。そこで、LCA算定と並行して一緒にサプライチェーン連携を作る枠組みに参加しました。
――富士通の取り組みに参加するに当たって懸念点はありませんでしたか。
寺田氏:これまでに取り組んだことのないサプライチェーンでのデータ連携ということで、未知の不安もありました。CO2排出量を算出するためのデータを入力していくと、実際にどういった数値が出てくるのか予測ができなかったのです。しかも、その数値がビジネスに良い影響を及ぼすのか、悪影響を与えるのか、それもわかりませんでした。それでも、まずは枠組みに参加してみて、懸念払拭に向け発信していくことが望ましいと考えて参加しました。

情報通信ソリューション統括部門
ファイテル製品事業部門 ものづくり・STC推進部主査
寺田 幸平氏(取材当時)
もちろん参加することによる期待もありました。サプライチェーン連携によりデータの「精度と鮮度」が向上すること、また、当社が実際にサプライヤーとして富士通にデータを提供することで、多くのサプライヤーが感じる不安や懸念などを実際に感じることができます。それが知見となれば、当社に部品や材料を納品しているサプライヤーに対して、どうアプローチすれば良いのかを考えるヒントにもなると考えたのです。
もうひとつは、古河電工としてのLCAを含めた環境活動PRになり得ることです。未知の領域だからこそ積極的に参加し、早い段階で課題感を共有することは自社の透明性や環境課題解決への姿勢を示す良い機会だと考えました。これらが参加を決めたおもな理由です。
鈴木氏:今回の取り組みは実際にサプライチェーンでデータ連携するので、当社のパートナーがどういう反応をするか、どれだけ協力を得られるかにも関心がありました。実際に行ってみることで本当の反応も見えてきます。その意味では、当社にとってもいつかはやってみないとならないことでした。今回は、背中を押してもらえた良い機会だったと感じています。
お互いに見据えているのは「サプライチェーン全体の脱炭素化」という信頼感が根底に
――参加にあたってはさまざまな懸念点もあったようですね。それらを乗り越えて実際に参加されて、どのようなことを感じましたか。
寺田氏:国際的な算定ルールに幅がある現状で、どのデータをどこまでの精度で出すかというルール決めが難しいと感じました。サプライヤーからの情報もどこまで出すかという判断も簡単ではありませんでした。
また、多くのサプライヤーがデータを連携させるのに躊躇してしまう理由の一つに、算出された数値によって、突然「CO2排出量が多い部品を納品しているサプライヤーとの取引を制限します」など、ビジネスに悪影響がでてしまうことへの懸念があると思います。正直に協力したのに結果としてデメリットになってしまう、そんなことがないよう、数値が絶対的な購入判断の材料とはならないことを発信していく必要があると感じました。

逆に言うと、そういった懸念が多少なりともあったにも関わらず、当社を含め多くのサプライヤーが参加したのは、根本に富士通との信頼関係があったからだと思います。お互いに目指しているのは「サプライチェーン全体のCO2排出量の削減」であって、サプライヤーを選定するためではない、見据えているものは同じはずだという安心感ですね。
――現在、お感じになっている具体的な効果や成果はどのようなものですか。
寺田氏:通信機器業界は市場環境による需要の増減が大きいので、直接的な需要の増加などは観測することが難しく、サプライチェーン連携を実際にやったことは価値があると感じています。また、富士通の取り組みやサプライヤー数社とのやり取りを通じて、現状で関係各社のLCAやCFP(カーボンフットプリント)についての課題感を知り、意見交換できたことも非常に良い経験になりました。
参加を決めたときの目的であるPRや連携実務の経験はほぼ達成されています。同時に、新たな課題として複数のパートナーに連携を広げていくことや、他システムを含めた情報の展開などが出てきたと認識しています。
また、実際にやってみると富士通のプラットフォームでCO2排出量を算出するためのデータを入力する作業もとても簡単でした。分かりやすいインターフェースで取り扱い説明書もあり、サポートも充実していました。例えば、製品ごとではなく、「工場の排出量」という大きな枠での入力もサポートされており、入力方法も数多く用意されていて「やりやすかった」という印象です。(注1)PCFデータの入力だけでなく、工場単位のLCA、CO2排出量データでも入力可能なため、PCF算定まで至っていない段階でも、恐れずに挑戦してもらいたいと思います。
より多くのサプライヤーと連携し、合理的にサプライチェーン全体のCO2削減を
――今後の展望についてお聞きします。今回の取り組みについて、古河電工としてはどのように活かしていきたいと考えていますか。
鈴木氏:より多くのサプライヤーとの連携を広げ、データを蓄積してCO2排出量の情報を共有化することによって、排出量の正確な把握と客観性を高めることと、サプライチェーン全体での効果的な削減活動を進めていきたいと考えています。他のシステムやプラットフォームとの連携を進められれば、情報の共有化が進み、全体のCO2削減が効率的にできると考えています。

また、今後は、サプライチェーンで集められたデータの相互活用など、富士通にもサプライヤーにも双方にメリットをもたらすデータ連携も期待できるのではないかと考えています。そんな話も実際にはでてきています。
寺田氏:今後は、今回のプラットフォームが他のプラットフォームやシステムと連携するようになって拡大していくことが望ましいと考えています。当社もアプローチできるところには、積極的に働きかけて参加や協力を依頼していきたいと考えています。
もう一つの方向性としては、「データの活用」についても検討が必要だと思っています。現状では算出されたデータは、おもにCO2排出量の増減を判断することに利用されています。例えば、火力発電所はCO2排出量が大きいホットスポットですが、排出量が大きいからといって単純に閉鎖すれば良いという議論にはなりません。CO2排出量のデータをもっと多く連携できれば、実際の経済活動や人々の暮らしと照らし合わせて、どこを削減していくべきか合理的な判断ができるようになっていくと考えています。データをどう活用して判断していくかが今後は重要になってくると思います。
――最後にフジトラニュースの読者に向けたメッセージをお願いします。
鈴木氏:今回のサプライチェーン全体の脱炭素化に向けた取り組みは、実データを用いた試みとして、古河電工にとっては非常に意義深いものでした。CO2排出量の算定や削減目標の設定は、おそらく多くの企業が着手していると思います。しかし、サプライチェーン全体の脱炭素化は個社単位で実現できる課題ではなく、連携して長期にわたって協力しながら実現していくべき共通の課題です。個社の利害やイニシアティブという狭い了見ではなく、我々が次の世代にどういった未来を残せるかというテーマだと考えています。より良い未来を後世に残すため、新たな価値観を持って、自ら一歩踏み出しましょう。その変化に期待し、行動に移すことが重要です。持続可能な未来を築くために協調し、次の世代に誇れる社会と地球を残すことは我々の使命です。
寺田氏:CO2排出量の削減は、じつは効率化にもつながることです。そう考えると、企業にも個人にもできることはもっとあるはずです。CO2排出量を「減らす」ばかりに目が向いてしまうと「数値を下げれば良い」と思われてしまいますが、もっと前向きに仕事の効率を上げる、工場の生産性を高めるための改善策を考えるといった方向で取り組むことができるのです。CO2排出量とは効率的な工場の運用、仕事のやり方の指標であり数値であるので、そんな視点でみなさんも取り組んでいくことができれば理想的だと考えています。

情報ソリューション統括部門 企画統括部 企画管理第1部 業務課 山本氏
リスクマネジメント本部 環境部 主査 川上氏
情報通信ソリューション統括部門 ファイテル製品事業部門 ものづくり・STC推進部課長 鈴木氏(取材当時)
情報通信ソリューション統括部門 ファイテル製品事業部門 ものづくり・STC推進部主査 寺田氏(取材当時)
営業統括本部 セールス統括部 通信インフラ営業部 テレコムデバイス課 深原氏
関連情報
編集部おすすめ!
最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通
ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは
フジトラニュース編集部
「フジトラニュース」では、社会課題の解決に向けた最新の取り組みをお届けします。

編集部おすすめ!
最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通
ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す
「構造」と「リスク」を可視化しサプライチェーンをレジリエントに。東京海上グループ×富士通の取り組みとは

富士通の”いま”と”未来”が見える!「富士通統合レポート2024」3つのハイライト

「トマトから生まれた水」でインドを救う
~富士通のブロックチェーンが支える水不足への挑戦

