“知”をつなぐ、未来をつくる トヨタ自動車×富士通 モータースポーツ現場での生成AI活用

2025年9月17日
「もっといいクルマづくり」を追求するトヨタ自動車株式会社(以下、トヨタ自動車)と、最先端テクノロジーで社会課題解決を目指す富士通株式会社(以下、富士通)の両社はモータースポーツという共通のフィールドでの協業を進めています。トヨタ自動車の、レース車両のパワートレイン開発を担当するGRパワトレ開発部と、富士通による人材交流プロジェクトが2024年7月に始動し1年が経過。現場ではどのような変化が生まれ、また持続可能なモビリティ社会の実現に向けてどのような未来を描いているのか。実際にプロジェクトを推進しているメンバーに話を聞きました。
(表紙左から)
富士通 トヨタユニット Zhao Ruiwen
トヨタ自動車 GRパワトレ開発部 小倉 隆聖 氏
富士通研究所 赤崎 拓未
人材交流プロジェクト始動から1年、現場ではどのような変化が起きているのか
――富士通社員の現場への出向、また富士通とのプロジェクトを推進していく中で、GRパワトレ部内での変化はありますか。
小倉 氏:大きな変化を感じています。もともとトヨタ社内だとDXの取り組みが他部門と比べて遅れている部分もありましたが、富士通様と一緒にプロジェクトを推進していく中で、自動化や生成AIの活用方法について知見が深まり、実際に業務へDXを取り入れる動きが加速していると実感しています。特に、富士通様から出向していただいているご担当者の推進力は非常に大きいと感じています。技術的なご支援だけにとどまらず、トヨタ内の他部署とも積極的につなげていただくことで、部としても社内で先進的なDXを実現できているという自信があります。こうした変化は、富士通様が現場に寄り添い、一緒に課題に挑戦してくださる姿勢があってこそだと思っています。
――GRパワトレ開発部と現在進めているプロジェクトの概要を教えて下さい。
Zhao:製造業界では、後継者不足などによりナレッジを伝承できないという大きな課題がありますが、モータースポーツ現場も例外ではありません。このような課題を解決する為に、GRパワトレ開発部の技術者が長年にわたり蓄積してきたハイパフォーマンスパワトレーン開発・チューニングの経験や分析手法などのノウハウを、当社の生成AI技術を活用してデジタル化し、組織ナレッジへと転換する取り組みを進めています。
具体的には現在、生成AIを活用したエンジン制御モデルの解読に取り組んでいます。モータースポーツ現場では、エンジンの開発フェーズに留まらず、レースの度にサーキット特性や、テクニカルレギュレーションに適したセッティング変更が必要となり、熟練のエンジニアが非常に複雑な制御モデルの変更に対応されています。制御モデルの解読を生成AIでアシストすることで、対象変更箇所が効率的に絞られ、エンジニアが高度な制御仕様の調整作業に注力することが可能になります。
――プロジェクトを推進してく中で、現場理解も深まっているかと思いますが、ご自身の業務や思いに変化はありましたか。
Zhao:強く感じたのは、「常に未知領域へ挑戦する喜び」です。これまでのプロジェクトでは主にサンプルデータを使った検証が中心でしたが、今回は現役レース車両の設計データを扱うことで、実データの大きさや複雑さに直面し、チームメンバーと共に未知の課題に挑み続ける毎日です。その過程で実感したのが、「チームワークの重要性」です。社内で前例のない取り組みだったため、研究所をはじめとした異なる専門知見を用いたメンバーと連携し、協力しながら困難を乗り越えてきました。こうした経験を通じて、技術だけでなく挑戦する姿勢や達成感、そして仲間と共に協力する大切さを学び、自分自身の成長に大きく繋がっていると感じています。

レーシングカーのエンジン開発現場で鍛え上げている富士通の技術とは?
――富士通研究所は、本プロジェクトでどのようなテクノロジーを鍛えているのでしょうか?モータースポーツという究極の現場に入ることで挑戦出来ていること、また期待はありますか?
赤崎:技術面では「知識の融合」に挑戦しています。レースに勝てる強いマシンを制作するには、個々人が高い専門知識を備えていることも重要ですが、それ以上にメンバー間の連携が何よりも重要です。お互いの専門知識を理解し、暗黙知を共有し、意見をぶつけながら方向性を決める、とても時間と根気の要る連携です。
富士通ではKG拡張RAG for SE (注1)やKG拡張RAG for QA(注2)などの各領域の特化型生成AIを研究・開発してきましたが、「現場」ではそれらの融合が重要です。AIによる知識融合というのは研究面でも非常に面白いテーマです。知識グラフRAG・マルチエージェント等の手法がものづくりにおける人々の相互理解にどれだけ役立てるか、やれるだけのことをやってみようと思います。
――研究所の加入で、本プロジェクト及びレーシングカー開発現場での富士通のテクノロジーを活用する可能性は広がっていますか?
Zhao:富士通研究所が持つ最先端の技術や知見を導入することで、モータースポーツ分野での技術活用の幅が飛躍的に広がりました。モータースポーツの開発現場では、設計から実装までが量産よりもはるかに短いサイクルで進み、複雑な課題に対してスピーディーな成果が求められます。こうした厳しい環境にも、先進的で柔軟な技術が力強くサポートしています。富士通研究所の技術は現場のニーズに合わせてさらに磨かれ、高いパフォーマンスを発揮できるよう進化し続けています。そして、将来これらの高度な技術は自動車産業をはじめ、さまざまな製造業の現場でも幅広く活用され、多様なニーズに応えるソリューションとして展開していくと強く感じています。
現場で生成AI活用をすることで描く、持続可能なモビリティ社会の未来とは?
――現在取り組まれている生成AI活用のプロジェクトが、持続可能なモビリティ社会の未来の実現にどう貢献していくのか、現場目線で皆さんがどう感じているか、教えて下さい。
小倉 氏:今の自動車業界はコモディティ化が進んでいると感じています。このままでは、トヨタもコモディティ化の波に飲み込まれてしまい、持続的な成長が難しくなってしまうかもしれません。私たちGRカンパニーが目指す「モータースポーツを起点としたもっといいクルマづくり」は、コモディティ化への対抗手段になると考えています。
モータースポーツではドライバーが勝てる車が求められます。この「勝てる車」こそが「良い車」につながると私は思っています。勝つための車づくりには、限られた人数で課題を素早く解決していく力が必要ですが、生成AIを使えばより効率的に課題解決が進み、勝利へと近づく鍵になるはずです。これは個人的な野望なのですが、モータースポーツで鍛えられた生成AIが、量産車の開発にも活かされていけば、モータースポーツのエッセンスを取り入れた面白い車がもっと世の中に提案できるのではないかと考えています。私はそんな未来のモビリティ社会を見てみたいですね。
赤崎:持続可能というのはゴールじゃなくて、今の世代が今できることを一つ一つ解決し続ける心構えのことだと思っています。格差・環境、ひとつ問題を解決したら、必ず次の課題がやってきます。我々技術者はそれに向き合い続けることが大切です。
人間、ひとりでは頑張り続けられません。周囲の人から受けるエネルギーが必要です。世の中をよくしたいと思うモチベーションを持続していくために、私は「AIによる知識の融合」を通して、人々が隣の人の頑張りを感じて今日のエネルギーを得られるような、そんな社会を作っていけたらいいなと思っています。
Zhao:持続可能なモビリティ社会の実現には、複雑な情報をもとに素早く判断する力が不可欠です。その力を養う絶好の場が、まさにモータースポーツの開発現場です。技術を磨くだけでなく、富士通の多様なメンバーがVUCA(変動性・不確実性・複雑性・曖昧性)を体験できるこの現場に関わることで、複雑な状況への対応力を強化できます。これにより、将来、持続可能な社会の構築において直面するであろう複雑な課題にも果敢に取り組み、解決できるスキルが身につくと確信しています。
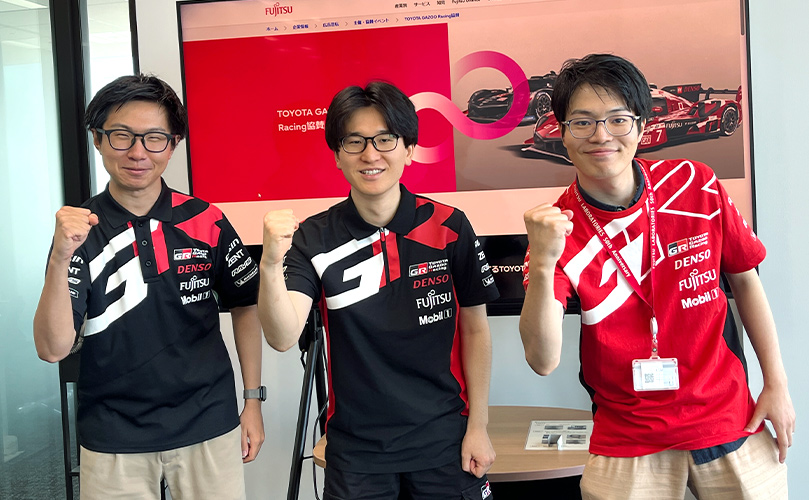
関連情報
編集部おすすめ!
最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通
ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

この記事を書いたのは
富士通株式会社エンタープライズ事業トヨタユニット(モータースポーツチーム)
私たちモータースポーツチームは、WEC世界選手権に参戦するTOYOTA GAZOO Racingさんを応援し、モータースポーツへのテクノロジーによる貢献を目指し日々活動しています。

編集部おすすめ!
最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

UR都市機構×富士通
ゼロトラストで実現するセキュリティと利便性を両立した次世代基盤

類似記事を探す
最先端研究施設で産学連携の成果を体感し、多様な研究者と議論して得られた「気づき」とは?

学術を探求するアカデミアや博士人材と富士通はどう向き合うか?~SRLパネルディスカッションで大学と富士通が白熱の議論~

羽生善治×富士通研究所所長が語る。AIと人間が共存する未来への展望


![[ロゴ] TOYOTA GAZOO Racing](/-/media/Project/Fujitsu/Fujitsu-HQ/local/blog/article/2025-09-17-01/logo_01_700x375.jpg?h=375&iar=0&w=700&rev=ad432faa656446119adc1adf05b81656&hash=9C579C8DC142199F9530E1E355558BE5)